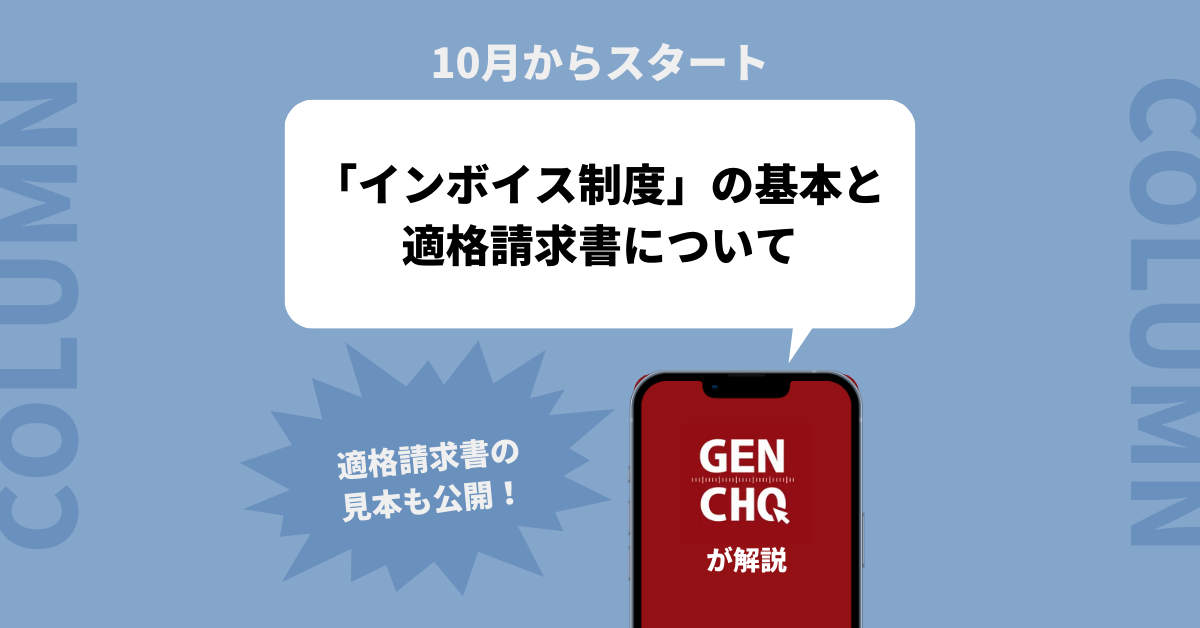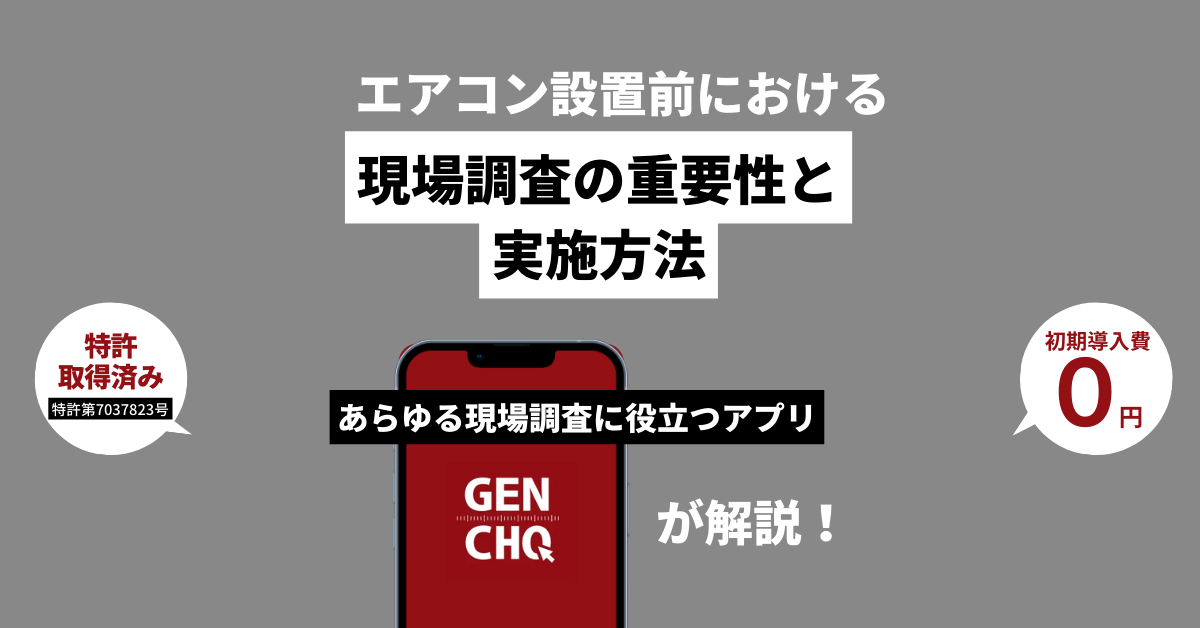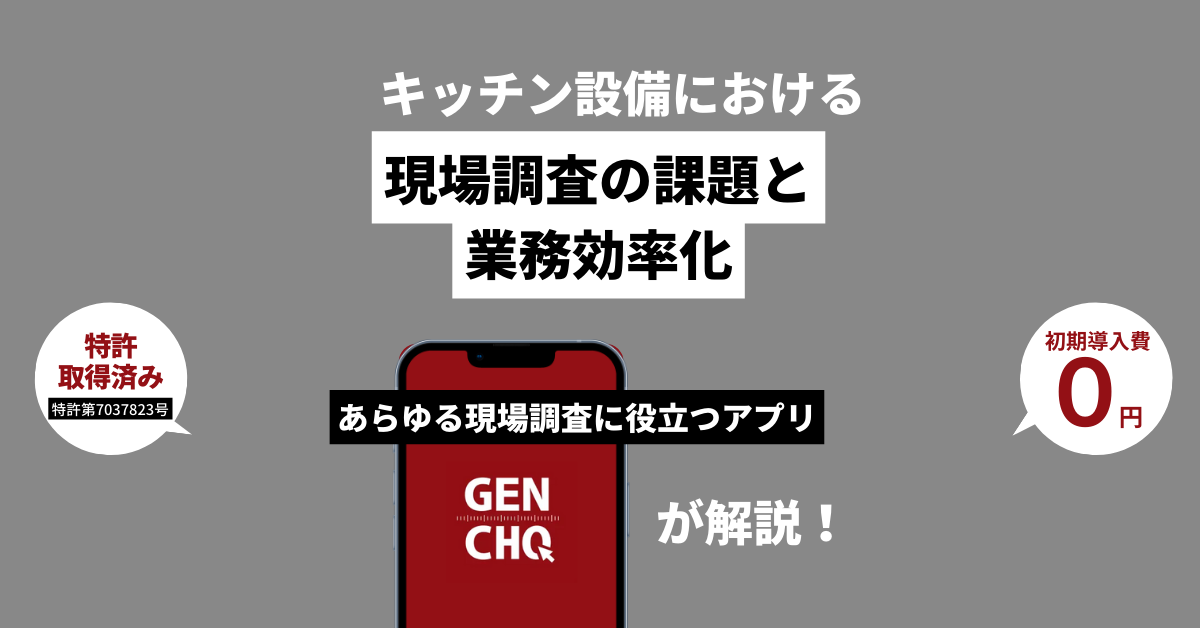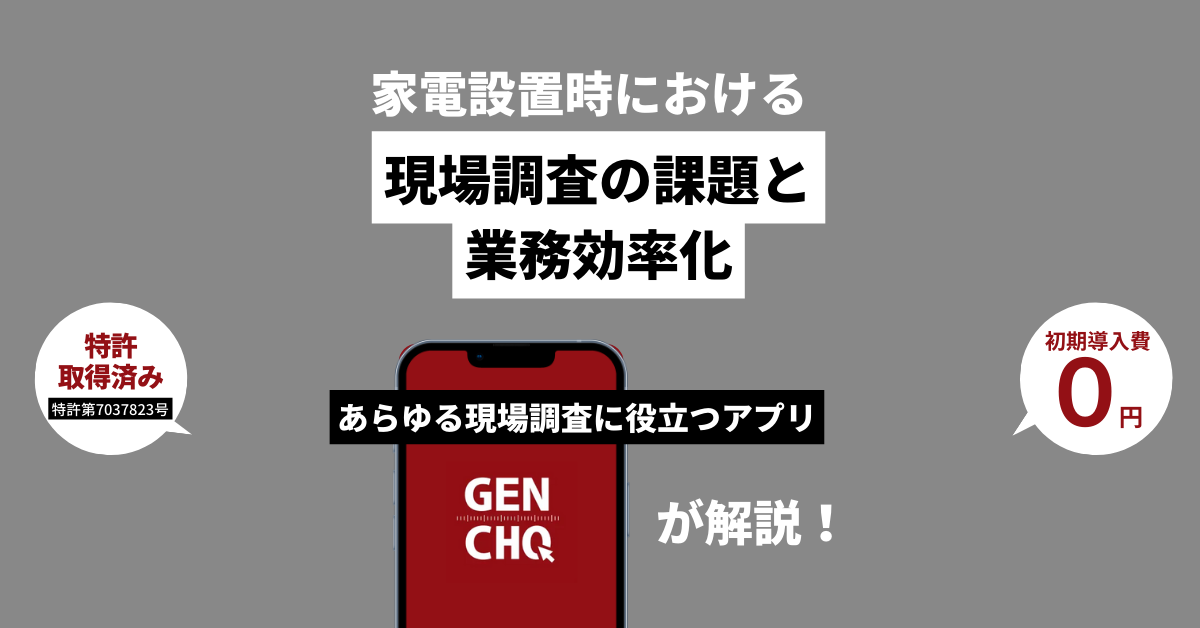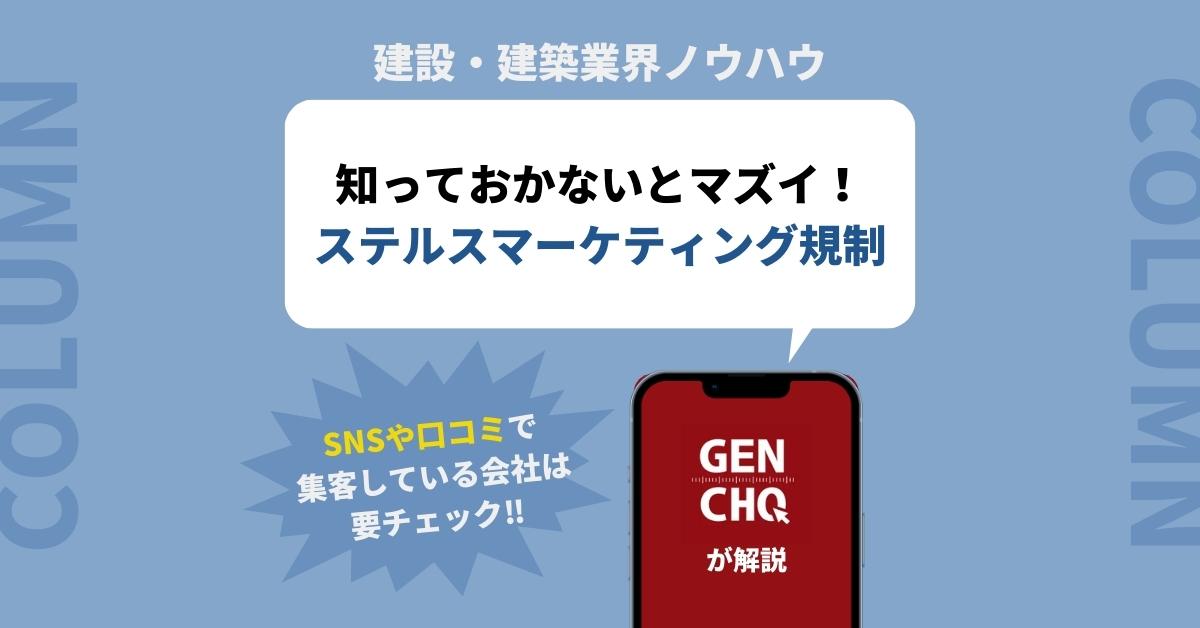
このブログではこんなことがわかります
- ・景品表示法とは
- ・ステルスマーケティングとは
- ・ステルスマーケティング規制の内容
「景品表示法」(消費者庁HPより抜粋)とは
正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。 「景品表示法」は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。「ステルスマーケティング」とは
広告やプロモーションが広告であることを隠して行われることを指します。 消費者保護の観点から問題視されることがあり、多くの国で規制やガイドラインが存在します。 建築関連事業者の皆さんも、食事をする時や旅行する時、旅行先での宿泊探しをする時に、そのサイトの口コミやレビューを参考にして探しませんか? それと同じように、あなたの会社のお客様も、会社の口コミを参考に見積や来店を検討します。 でも、この口コミが、例えばリフォーム会社側が頼んだサクラやリフォーム会社のスタッフだったらどうでしょうか? その真相や中身は私たちではわかりませんよね? 現にそういった事例もあり、過去ニュースに取り上げられるような大きな問題にもなりました。「ステルスマーケティング」の種類
「ステルスマーケティング」は大きく分けて2種類あります。- ①なりすまし型
- ②インフルエンサー型
①なりすまし型
情報を発信する会社が一般消費者になりすまして、好意的な口コミやレビューを投稿すること。
②インフルエンサー型
広告主やリフォーム会社から依頼された芸能人やインフルエンサーが、宣伝であることを隠して商品を紹介すること。 どちらにしても消費者に広告だとわからずに宣伝することはステルスマーケティングにあたります。
消費者が広告であると認識せずに商品やサービスに接触する可能性があります。
そして、報酬の有無は関係ありません。無報酬でも宣伝ということを隠していたら、これらにあたります。
どちらにしても消費者に広告だとわからずに宣伝することはステルスマーケティングにあたります。
消費者が広告であると認識せずに商品やサービスに接触する可能性があります。
そして、報酬の有無は関係ありません。無報酬でも宣伝ということを隠していたら、これらにあたります。
ステルスマーケティング規制の一般的なアプローチ
ステルスマーケティング規制の一般的なアプローチとして以下のような点が考慮されることがあります。①広告の識別
ステルスマーケティングを防ぐために、広告やプロモーションが広告であることが明確に識別可能であることが求められます。 これには、適切な表示やタグの使用が含まれます。
例
・「これはCMです」「これは広告です」
・文章中への「PR、AD、広告」などの表記
②透明性と正直さ
広告が広告であることを隠さず、正直な情報を提供することが要求されます。 虚偽の情報を提供することや、商品やサービスの性能を誇張することは規制の対象となることがあります。
例
・分割料金の表示であたかも低価格のように表示はNG
・販売価格よりも高い価格を併記することにより、あたかも、実際の販売価格が安いかのように表示はNG
③ソーシャルメディアとインフルエンサー
ソーシャルメディアやインフルエンサーを通じて行われる広告も含めて、広告であることが明確になるようなガイドラインが設けられることがあります。 インフルエンサーが報酬を受け取って商品を宣伝する場合、その関係が明示されることが求められることもあります。
例
・タイアップラベル等の設定(InstagramやYoutube)
・「モニタープレゼントに当選しました」「A社からご提供いただきました」など関係性を明確にする
④コンテンツマーケティング
コンテンツマーケティングの場合、広告的な要素が含まれる場合でも、そのコンテンツが広告であることが明確になるように配慮する必要があります。
例
・取材記事のようにすることで広告として認識されにくくする行為はNG
・企業タイアップ案件であることを隠して、検証動画と題してYoutube動画を投稿するのはNG
違反した場合は?(※消費者庁HPより抜粋)
景品表示法に違反する不当な表示や、過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。 調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。 違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は「指導の措置」が採られます。 また、事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じる(課徴金納付命令)と書かれています。2023年10月より注意すべき点は?
建築関連事業者の皆様におかれましても、掲載済みの口コミなどがステルスマーケティングに該当していないか?を調べて、該当する場合は、広告の掲載を中止、または広告であることを明示するなどの対応が必要になります。 「知らなかった」ではすまされません。 投稿者と事業者に明確な依頼がない場合でも何かしらの対価を受けられる関係にある場合や、投稿者の自主的な投稿と認められなければ、規制の対象となりうるので、皆様、気をつけましょう。更に理解を深めるには
消費者庁のHPには、ステルスマーケティングについてのガイドブックがあり、事例やイラストで更にわかりやすく解説されています。 こちらも参考にしながら、正しい表示、正しいマーケティングを実施していきましょう。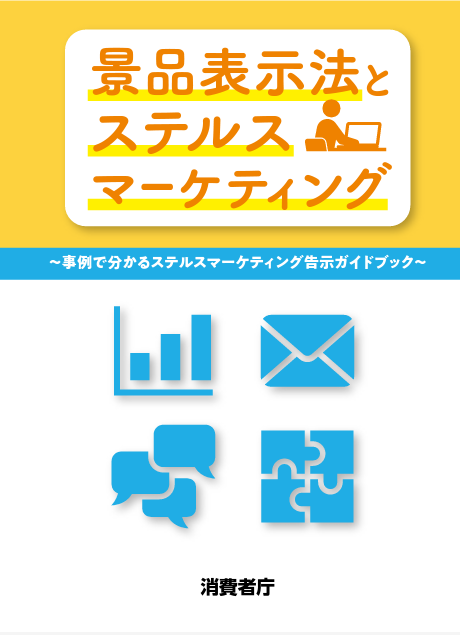 画像引用:景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック/消費者庁
画像引用:景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック/消費者庁